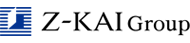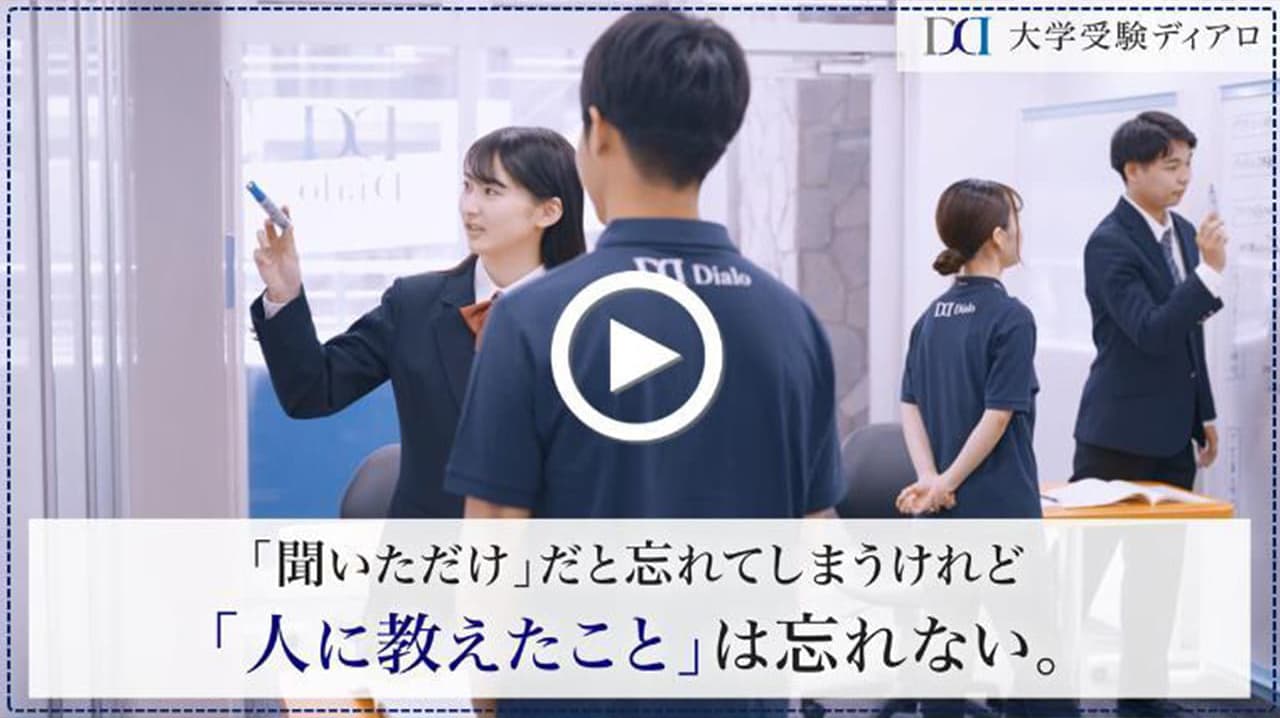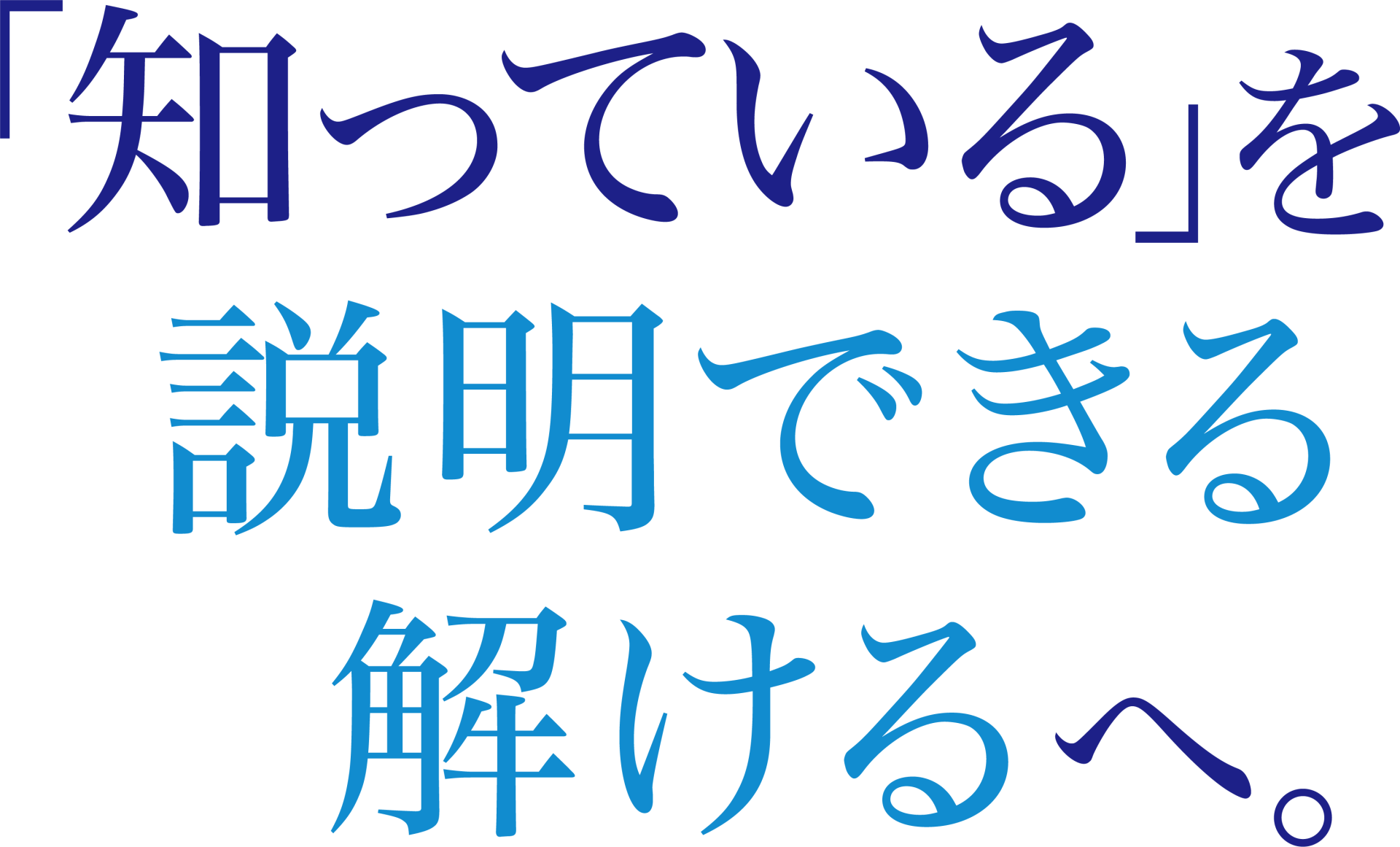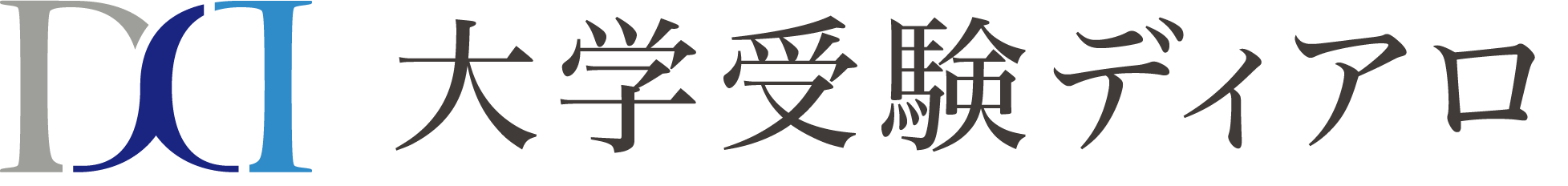- 大学受験の学習塾ディアロ(Z会グループ)
- コラム
- 新着記事一覧
-
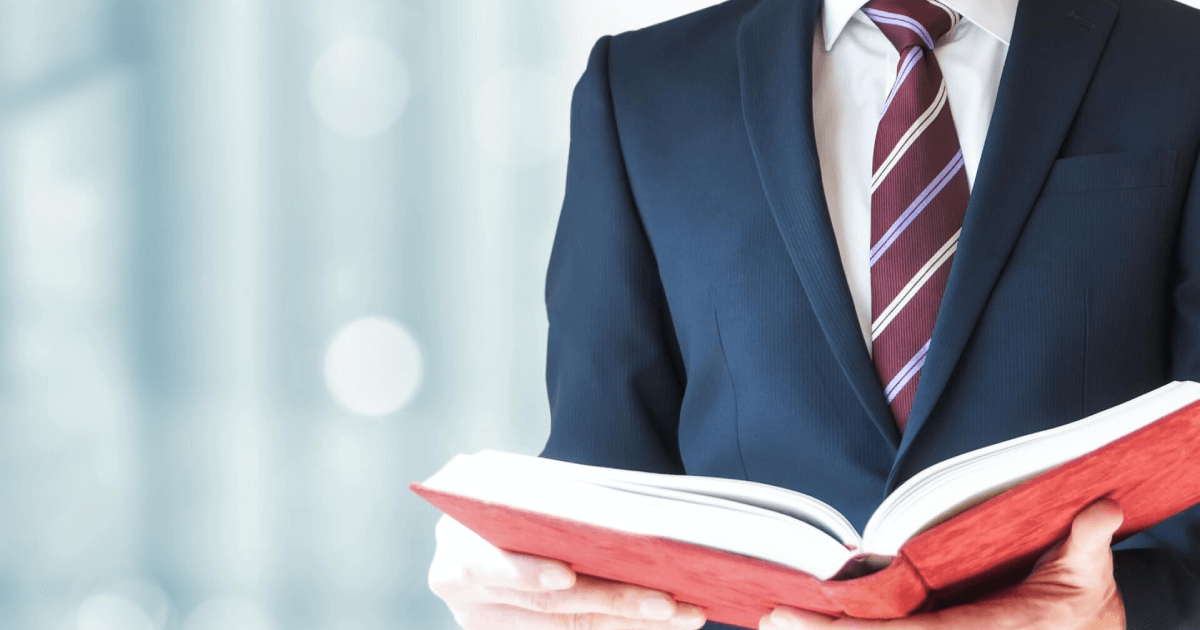
勉強法
現代文の勉強法|定期テストや共通テスト対策をわかりやすく解説
現代文は、読解や解答のポイントを押さえれば誰でも高得点が狙える科目です。なぜその解答にたどり着いたのか、自分の言葉で説明することから始めてみてください。現代文のように答えがひとつでない科目こそ、適切な知識と経験のストックが必要です。
-

勉強法
志望理由書の書き方(大学)・構成例や学部別の記載例を解説【例文・NG例つき】
大学の志望理由書は、学校推薦型選抜や総合型選抜の書類・面接選考で用いられる書類です。志望理由書では「なぜその大学・学部でなければならないのか」を、文章で伝えなければなりません。表現力を養成するには、アウトプットを重視した専門的なトレーニングが必要です。アウトプット学習のノウハウがある大学受験専門塾で早めにトレーニングを始めましょう。
-

大学受験・入試情報
大学受験の面接で使える自己PRを例文付きで解説【高校生必見】
面接では、限られた時間のなかで自分を表現しなければなりません。しかし、大学入試で自己PRスキルを磨いておくと、その後の就職活動だけでなく社会に出てからも役立ちます。面接では誰もが緊張するものです。緊張はつきものだと割り切り、たくさん練習して場慣れしましょう。
-

勉強法
化学の勉強法!大学受験の対策を分野別に解説【高校生向け】
大学受験に向けた高校化学の勉強は、膨大な量の暗記や計算問題に立ち向かう必要があります。難解な内容に苦手意識を持つ受験生も多いですが、コツをつかんで、1STEPずつクリアしていけば、最後には必ず理解できるようになります。適切なサポートを得ながら、インプットだけではなくアウトプットを重視した勉強を進めていきましょう。
-
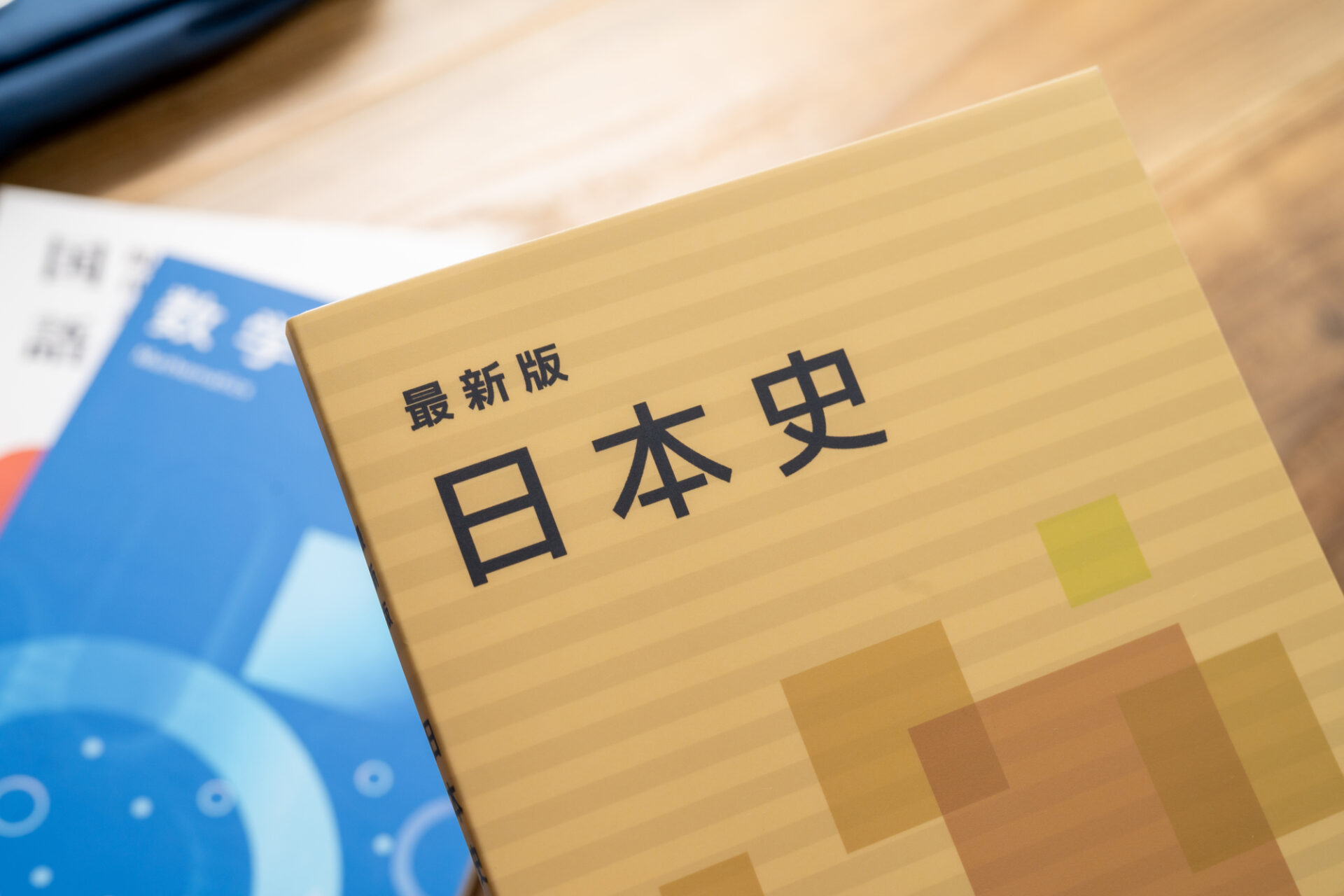
勉強法
日本史の勉強法!大学受験・入試対策で周りと差をつける効率的な方法
大学受験の日本史の勉強は、非常に広い出題範囲が特徴です。また、2025年からは新課程の入試になるため、入試傾向が変わる可能性もあります。漫然と板書をノートに書き写していたり、闇雲に過去問に取り組んでいたりするのではなく「アウトプット」を重視してポイントを押さえた勉強を進めていきましょう。大学受験ディアロの「1:1対話式トレーニング」で、アウトプット学習を体感することをおすすめします。
-

勉強法
大学受験の勉強法!いつから始める?何から始める?スケジュールの立て方とやり方を解説
「大学受験に向けて勉強を始めよう」と思い立っても、勉強する範囲が広いことに気づき、どこから手をつけたら良いかわからないと悩んでいる人は多いのではないでしょうか。 大学受験までの時間は限られるため、できるだけ効率良く勉強したいと考える人も多いはず。 この記事では、大学受験の勉強においてまず始めるべきことや、合格するための勉強法のほか、各科目の勉強法などについて基本的な事項をまとめて解説します。 受験…
-
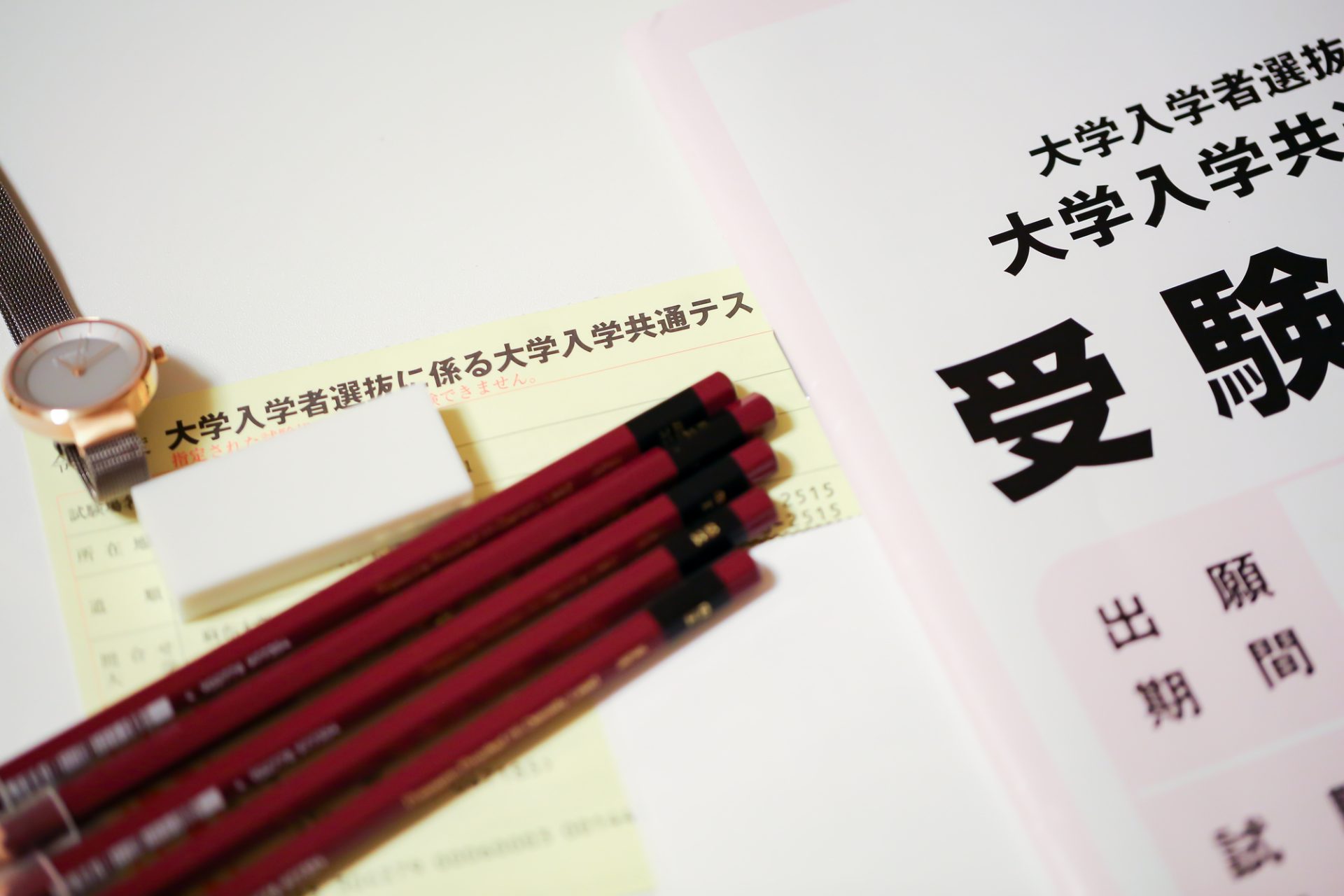
大学入学共通テスト
大学入学共通テストの日程・時間割・科目|共通テスト対策を解説
共通テストは、平均点5割程度を前提に設計されたテストです。高校教育の基礎をしっかりインプット・アウトプットし、マークシート方式に慣れつつ、時間配分についての戦略を立てれば、一定以上の得点が見込めます。さらに「なぜ?」「どうして?」と深掘りながら過去問を解いていけば思考力・判断力も身に付くはずです。インプット・アウトプット学習を活用しながら、自分に合った勉強方法や共通テストを解く際の戦略を考えていきましょう。
-

勉強法
大学受験英語の勉強法!志望校合格に向けてレベル別に解説
英語力は一定レベルに達すると、「ツール」から「スキル」に変わります。大学受験の勉強は、そんな本物の英語力を身に付けるチャンスです。そのためには成果が出せる英単語・英文法のインプットと英文読解練習、それを計画的に進められるようなサポートも必要です。大学受験ディアロのインプット・アウトプットを重視した英語学習で、英語の文法力と読解力を身に付けましょう。
-

勉強法
旧帝大の各大学偏差値・特徴・難易度|合格に必要な勉強時間も解説
旧帝大の入試は、教科・科目数も多い上に出題難度も高いのが特徴です。時間が限られているため、高校1年生の早い段階から英・数・国の3教科の基礎固めに着手し、授業内容を確実に習得していく必要があります。国公立大専用カリキュラムでアウトプットを重視し、効率良く計画的な勉強を進めていきましょう。
-

勉強法
【高校生向け】歴史総合の勉強法は?暗記から理解型に変える5ステップ
「歴史総合のテストでなかなか点が取れない」「勉強方法がわからない」と悩んでいませんか? 歴史総合は、2022年度から始まった必修科目です。従来の日本史Aと世界史Aを統合し、主に18世紀以降の近現代史を日本と世界を横断しながら学びます。 従来の暗記中心の歴史学習とは異なり「なぜそうなったのか」を理解することが求められる科目なため、用語を覚えるだけでは、定期テストや入試の記述問題・資料問題で得点できま…
カテゴリー
人気のタグ
人気記事TOP5
\入力1分!お悩み相談はこちら/