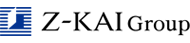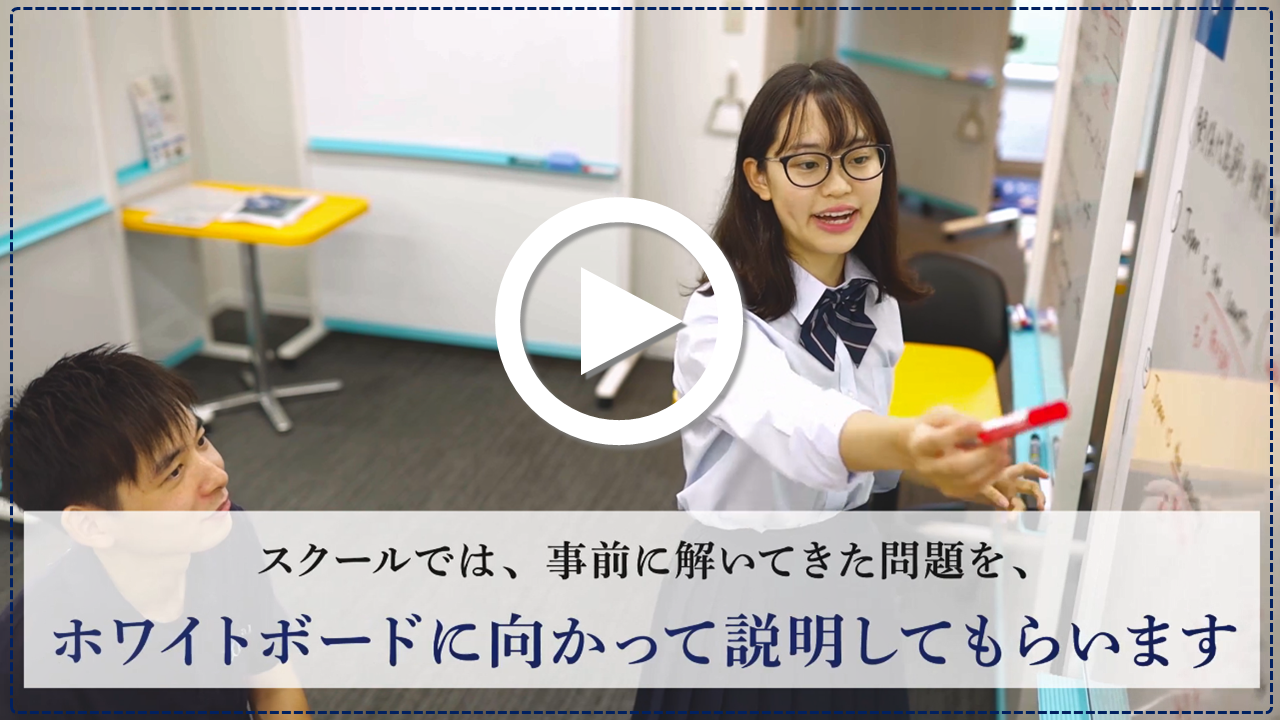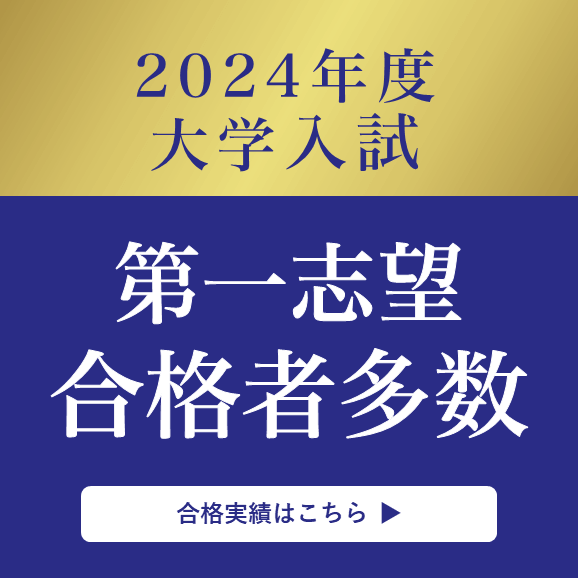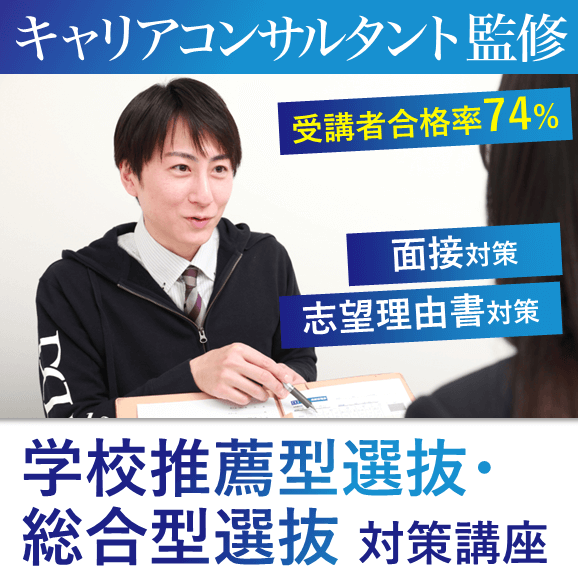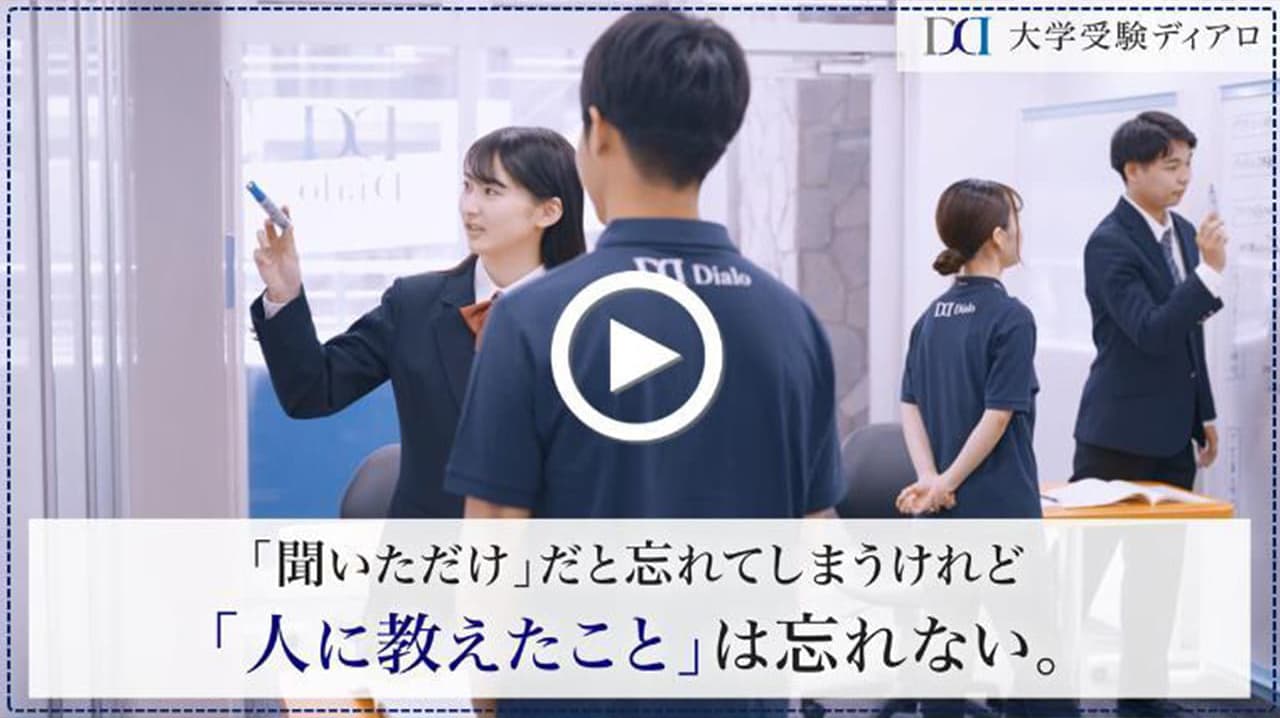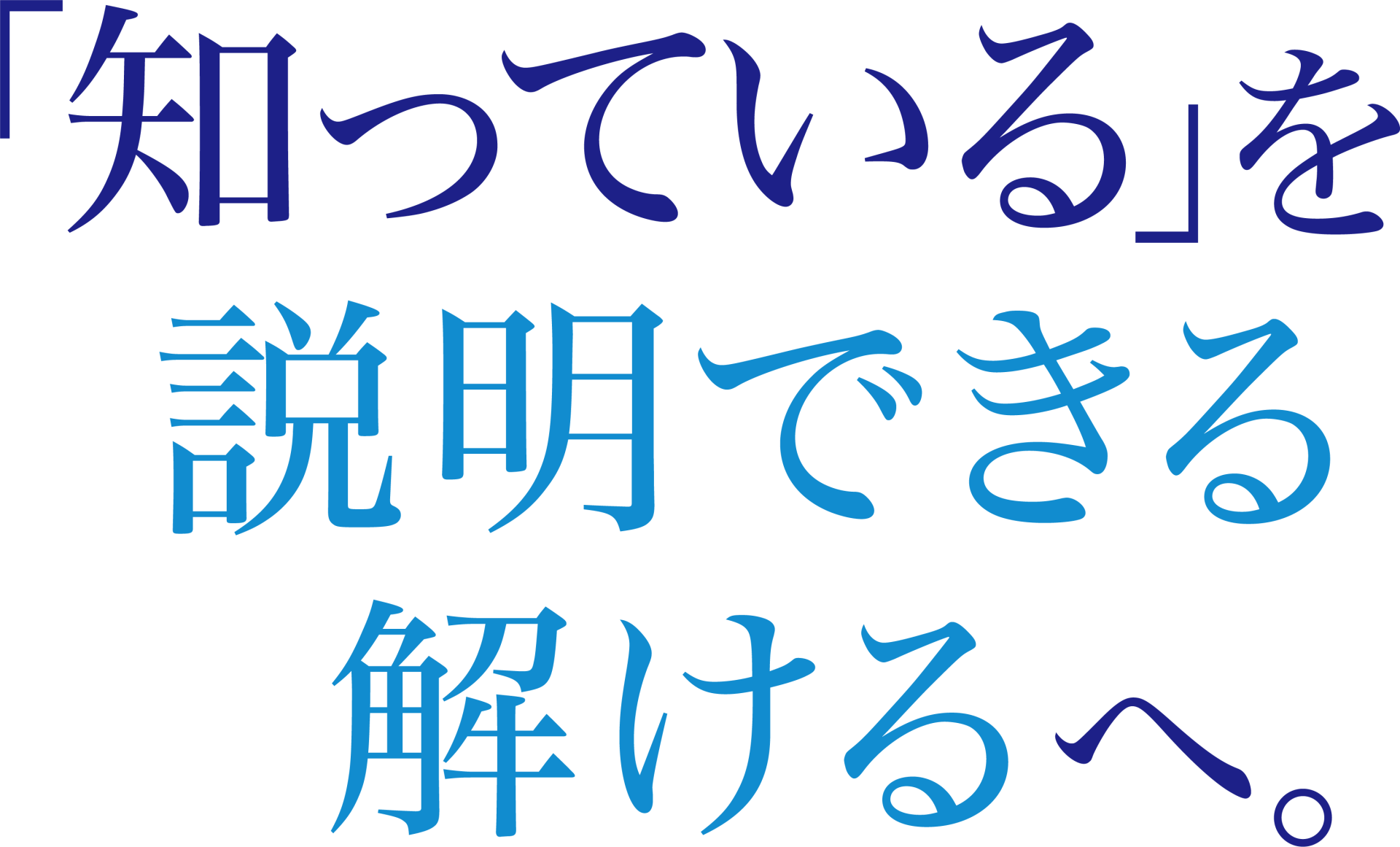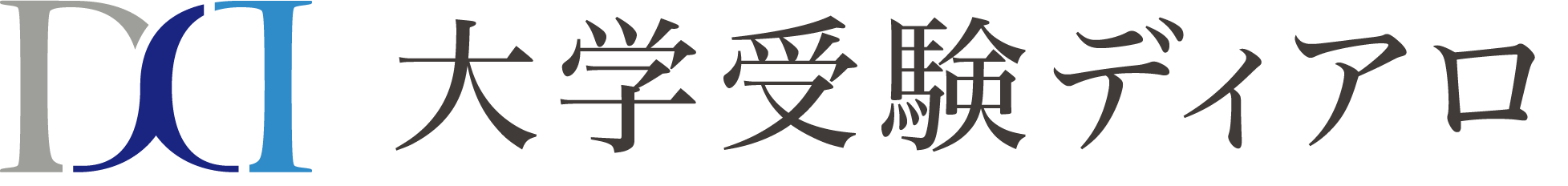- 大学受験の学習塾ディアロ(Z会グループ)
- コラム
- 大学受験・入試情報
- 私立大学のセンター試験利用入試とは?合格ボーダーラインも紹介
大学受験・入試情報
私立大学のセンター試験利用入試とは?合格ボーダーラインも紹介
近年、大学入試は多様化してきました。その代表格と言えるものが私立大学のセンター試験利用入試です。皆さんも一度は耳にしたことのある入試方式の一つではないでしょうか。そして、このセンター試験利用入試にどのようなイメージを持っていますか?
今回は知っていたようで意外と知らなかった私立大学のセンター試験利用入試の特徴やメリット、デメリットをお話しします。
▼あわせて読みたい!
センター試験とは?
センター試験利用入試とは
皆さんが真っ先に思い浮かべる私立大学の一般的な「入試」は、各大学に出願し、各大学側が作った問題で試験をおこない、その結果で合否を決めるものです(「一般入試」と呼ばれる入試方式です)。一方、センター試験利用入試は、センター試験の得点結果を、大学側が合否判定に利用するというものです。センター試験利用入試を利用する大学は年々増え、今では約530校の私立大学で利用されています。特に、首都圏の主要大学では慶應義塾大学、上智大学、学習院大学、学習院女子大学、聖心女子大学を除くほぼ全ての大学で採用されています。センター試験利用入試で受験する場合、受験生は大学への出願のほかに、大学入試センターに出願しセンター試験を受ける必要があります。センター試験利用入試の出願日程や選抜方法は各大学で決定されます。そのため、センター試験の受験科目や、センター試験の結果のみで合否が判定されるのか、それともセンター試験と各大学の個別試験も実施されるのか、は各大学・学部によって異なります。まずは各大学の募集要項を確認し、大学への出願の日程、選抜方法、入試科目などを確認しておくことが大切です。
例:
●千葉工業大学
センター試験利用入試で全学部・学科の出願が可能。
●東京理科大学
A方式:センター試験の結果のみで合否判定を行う。A方式では1学科のみ出願が可能(昼間学部)。
C方式:センター試験(英語・国語)の得点と大学の個別試験(数学・理科)の得点の合計で合否判定を行う。
C方式では2学科まで出願が可能。また、A方式とC方式の併願は可能。
センター試験利用入試の合格ボーダーライン
「ボーダーライン」という言葉をよく耳にするかと思います。今までにも、この「ディアログ」記事内で使ってきた言葉です。そもそも「ボーダーライン」とはどのような意味なのでしょうか?
それは、「合格者と不合格者の数がほぼ半数になっているライン」のことです。当然ですが、ボーダーラインは各大学によって異なってきますので、HPなどで確認しておきましょう。
センター試験利用入試は一般入試に対して募集人数が非常に少ないので、倍率が高くなりがちになり、ボーダーラインも上がる傾向にあります。多くの学校は入試科目が複数設置しており、その中から自分で選択する方式を取っていますが、科目数が少なければ少ないほど倍率やボーダーラインが上がりやすいです。
以下は明治大学政治経済学部経済学科の例です。一般入試方式とセンター試験利用3科目方式と7科目方式のそれぞれの募集定員とボーダーライン、倍率をまとめたものです。
例:明治大学 政治経済学部経済学科2019年度入試
一般入試方式(募集定員:290名)→ボーダーライン71.1% 倍率3.5倍
センター試験利用3科目方式(募集定員:20人)→ボーダーライン89% 倍率6.2倍
センター試験利用7科目方式(募集定員:50人)→ボーダーライン80% 倍率1.6倍
ご覧の通り、センター試験利用3科目方式ではボーダーラインが約90%で倍率も6倍以上と非常に厳しい勝負になりました。それに対し、7科目方式のボーダーラインは約80%となり標準的な難易度、倍率も1.6倍まで落ち着きます。
データだけ見れば7科目方式の方が圧倒的に有利になりますが、こちらは7科目入試となるので、私立大学専願の受験生にとってはセンター試験だけのために勉強する科目が増えるというデメリットもあります。どちらを選ぶかは皆さんの学習状況次第となると思いますので慎重に決める必要があります。
>【Z会グループ】大学受験「ディアロ」は学習相談を受付中。学習相談のお申し込みはこちらから
センター試験利用入試を受験するメリット
センター試験利用入試は一般入試に対して募集人数が非常に少ないので、倍率が高くなりがちになり、ボーダーラインも上がる傾向にあります。多くの学校は入試科目が複数設置しており、その中から自分で選択する方式を取っていますが、科目数が少なければ少ないほど倍率やボーダーラインが上がりやすいです。
また出願のタイミングも、センター試験前の出願と、センター試験後の出願があります。
特にセンター試験後の出願では、自己採点結果と例年の合格ボーダーラインをもとに、ある程度合格の可能性が高い大学に出願することができるメリットもあります。
さらに、センター試験は1月におこなわれ、ほとんどの大学の一般入試よりも前になるため、各大学の入試本番に向けてモチベーションを高めることができることができます。例えば、上智大学を第一志望とした場合、試験日程は2月の上旬とかなり早い時期に一般入試が実施されるので併願が非常に組みにくくなります。その時にセンター試験利用入試で複数校出願をしておけば自己採点結果をもとにおおよその合格可能性は判断できるというメリットがあります。
センター試験利用入試を受験するデメリット
メリットでもお伝えした通り、1回の試験で多数の大学を受験できるので、その分多くの受験生が出願し、一般入試よりも難易度(合格最低点)が高くなる傾向にあります。特に一般入試に比べて募集人数が非常に少ないこともあるため、倍率は非常に高くなります。
また、受験する大学・学部のセンター試験利用入試で、一般入試で必要な科目以外の科目が必要になるという場合、一般入試のみの場合に比べて学習すべき科目が増えることになるため、センター試験のためだけにその科目をどの程度学習すべきかについても兼ね合いを考える必要が出てきます。
また、複数の大学・学部・方式に出願すればそれだけ検定料も払うことになりますから、金銭面のことも考えて、出願する大学・学部・方式の数を決めていきましょう。その際には前述の「一般入試と併願で割引になる」などの各大学の特典なども確認しておきましょう。
Z会グループの個別指導塾
「大学受験ディアロ」の対話式トレーニング
生徒満足度98.5%*「対話式トレーニング」を動画でご紹介しています。
ディアロの学習法は、従来型の「教える先生→教わる生徒」という一方通行の指導ではありません。
効率的なインプット学習と、生徒が主体の効果的なアウトプット学習による“反転学習”で、成績をのばし、志望校合格を目指します。
知識を定着させ、使えるようにするためには「人に教える」「人に説明する」ことが効果につながると、私たちは信じています。
ディアロでは、事前にZ会の映像で重要事項・知識をインプット。そして「ディアロの対話式トレーニング®」で、学んだことを自分の言葉で説明してもらいます。
その内容について、講師が様々な問いかけをし、たとえ正解でも「どうしてそう考えた?」と問いかけ理解の定着をねらいます。
わからない場合でも、すぐには答えを教えることはしません。「気づき」を与えるような質問を通して、考えを深めます。このように先生が生徒に教えるという一方的な授業ではなく、生徒が主体となるようなトレーニングを行っていきます。
「そんなの難しそう…」と思った方、大丈夫です。ディアロ生の97%*が「対話式トレーニングは楽しい」と回答しています。
お試しの無料体験トレーニングは随時受付しています。この効果の高い学習法を、「今」体感してみませんか?
※調査概要:大学受験ディアロ全在籍者(オンライン校除く)を対象に実施したアンケート調査(回答率85.5%),2020/12/15~2021/1/13,自社調べ。
詳しくは、ディアロ各スクールまでお気軽にお問合せください。
WEBからも24時間受付中です!
➡ お電話でのお問合せはこちら
➡ WEBからのお問合せはこちら
新着記事

勉強法
【大学受験】個別指導塾の料金は?失敗しない塾選びのポイント8選
「個別指導塾っていくらかかるの?」 「料金が家計に負担にならないか心配……」 このようにお悩みではないですか? 個別指導塾の費用は集団指導塾より高めですが、選び方によっては無理なく通い続けられます。ポイントを知らずに決めてしまうと、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。 この記事では、個別指導塾の料金相場や学年別の費用感、出費を抑えるための工夫、失敗しない塾選びのコツを分かり...

勉強法
【中高生】塾の料金は? 相場・学年別・塾のタイプ別費用を徹底解説!
「塾の料金ってどうしてこんなに高いの?」 「家計のことを考えると、このまま通わせていいのか不安……」 このように感じていませんか? 塾の料金は学年や授業形態によって大きく異なり、事前に調べずに選ぶと想定外の出費に悩むこともあります。しかし、費用の内訳や通い方の工夫を知っていれば、無理のない範囲で続けることも十分に可能です。 この記事では、中学生・高校生の塾費用の相場や塾代が高くなる理由、ご家庭に合...

勉強法
【中高生】塾の夏期講習の費用は?学年別の値段や受けるメリットを解説
夏休み前の三者面談や定期テストをきっかけに「塾の夏期講習に通おう!」と通塾を検討していませんか? その一方で、夏期講習の必要性を感じながらも「どのくらい費用がかかるのか」「うちの子に合った塾をどう選べばよいのか」と不安を抱えている保護者の方もいるでしょう。 あらかじめ費用や塾選びのポイントを把握しておかないと、想定外の出費につながったり、費用に見合う効果が得られなかったりする場合があります。 夏期...
カテゴリー
人気のタグ
人気記事TOP5
\入力1分!お悩み相談はこちら/